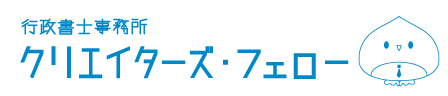約款とビジネスの創造
約款って何?
契約は当事者双方の合意で成立するのが原則です。ただ、多数の相手と同時に取り交わす場合など、個別の交渉は現実的ではありません。そこで、同一条件を提示した上で「これに合意する人だけ申し込んでくれ」という形をとる場合があります。こういう契約書を「約款」《やっかん》といいます。
約款による契約は、市民生活に深く食い込んでいます。例えば公共交通機関の利用がそうですし、保険なども、約款で細かなところまで規定されています(証書と一緒に送られてくる、細かい字でびっしりと印刷された紙が、保険約款です)。
かつて、約款を作るのは、ある程度大きなビジネスを行う企業に限られました。しかし、パソコンが普及してから、これが変わります。多くのソフトメーカーがユーザーに対し「ソフトウェア使用許諾契約」という名称で約款を突きつけるようになったのです。
媒体の入っている袋にこのように書いてあるわけで、これをシュリンクラップ契約といいます。
その後、オンラインを通じての配信も行われるようになると、ソフトウェアのインストール段階で同じことを要求されることが多くなりました。この場合をクリックラップ契約といいます。
これらの契約スタイルには、有効性について疑問視する見解もあったのですが、実務的に定着、先の民法改正で正式に認められました。

新しいビジネスと古い法律
クリエイティブ業界では、常に新しいビジネスが生まれています。今、私たちが水や空気のように当たり前に使っているサービス―例えばGoogleやAmazonも、インターネットの当初からあったわけではなく、普及していく段階で新たに登場したビジネスです。その後も、ミクシィ、モバゲー、楽天市場、2ちゃんねる、YouTube、Facebook、クックパッド、ホットペッパー、グルーポン、Uber――ブレイクしたものもあれば聞かなくなったものもありますが――と、次々と登場してきました。今後も同様に新しいビジネスが出てくるでしょう。そして、他ならぬあなた自身がその創り手になるのかもしれません。
ただ、法的には難しい問題が発生する場合があります。法律は制定時点で存在しているビジネスを前提に作られるため、それ以降に登場してきたサービスは想定外なのです。
当事者同士で特段の決めをしていなかった場合、民法の規定が適用されます。その結果、サイト運営者には、過大な義務が課せられてしまうことがあります。これは、大きなリスクです。
そこで重要になるのが、約款です。
といった形の約款を用意することで、サービス利用者の権利と義務を限定しておくのです。

ビジネスの創造のために
既存のビジネスに関する約款を作ることは、現実にはそれほど難しくありません。先行する他者のものを参考にすればいいからです。また、業界団体がひな形を作っている場合もあります。
しかし、新しいビジネスではこうは行きません。守るべきものをしっかり守れていて、かつ法的に意味がある文章を書かなければならないからです。また、ユーザーの反感を買わないように注意する必要もあります(不注意な書き方で炎上してしまう例が、しばしばあります)。そのビジネスが創造的であればあるほど、趣旨にかなった約款を作る困難さも増してくるでしょう。
とはいえ、ビジネスのコアなアイデアと直結しているため、うかつに他人に相談するわけにも行きませんね。その人が盗用しないにしても、「ねえねえ、ボクの知り合いでこんなビジネス始めようってしてる人いるんだけど、どう思う?」なんてツイッターで“リサーチ”されて一気に拡散……なんてことにもなりかねないのです。
そこで、専門職の出番です。
行政書士は、法に規定された専門職であり、守らなければならない義務をいくつも課せられています。依頼内容に関する守秘義務もその一つで、契約上の義務だけではありません。刑事罰があり、また懲戒対象でもある、法的な義務なのです。