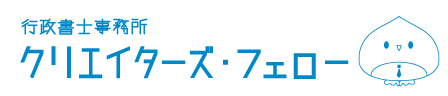独立開業から起業まで
そもそも独立ってどうするの?
クリエイティブ業界は、独立開業にそれほど抵抗感のない業界です。入社した時点で「君、いつまでうちにいるの?」なんてきかれたりすることもあります。とはいうものの、自分自身の問題となると、戸惑う点が多いでしょう。
独立開業したい人は、まず何をすればいいのでしょうか?
さしあたって必要なのは、仕事場と銀行口座、そして帳簿です。これらの用意ができたら、税務署に開業届を提出します。
実はこのあたりは本に書いてあります。「起業」や「副業」が時代のキーワードになっている今、書店に行けば、さまざまなガイドブックが並んでいるのです。もちろん専門的な概念もあり(例えば帳簿。『借方/貸方』とか『仕訳』とか言われても、勉強してないとちんぷんかんぷんですね)難しく感じらるかもしれませんが、実際に開業してからは実務としてこなしていかなければならないテーマですから、ここは理解してしまわないと。
ただ、ここで一つ問題があります。書籍で例示されるのは、小売りや飲食店のような一般的な起業。クリエイターの仕事にどう適用できるのかわからない場合が少なくないのです。

会社を作る場合
ゲームのようにチーム制作が前提になる分野ですと、仲間と一緒に会社を起こす、なんてこともあるでしょう。
こうなると、さらに難関となります。会社設立というのは、当事者の合意だけではできないからです。会社が会社として権利主体となるためには、設立登記されることが必要です。そして、設立には定款が不可欠ですし、さらに就業規則をはじめとした、さまざまな法的文書も必要になってきます。
例えば、社員が仕事時間中に行った創作でも、法の決まりでは、自動的に会社の著作物になるわけではありません。そのため、権利の発生と帰属について、雇用契約か就業規則でしっかりと定めておく必要があります。
こういうことをいい加減に進めてしまうと、後々会社の規模が大きくなってから困ることになりかねません。コアのエンジンを作ったプログラマが退職、同時に「あれオレの著作物だから、今後使うのやめて」なんて言い出したら、会社自体が立ちゆかなくなってしまうでしょう。

できることとできないこと
行政書士の主業務は「申請代理」と「書類作成」ですから、独立や起業のサポートにおいても、これらが中心となります。ただ、他士業の専管業務とされているものは対象外です。
まず挙げられるのが、税金関係。書類作成や申請代理は行政書士のメイン業務ですが、こと税金は別で、税理士の専管業務とされているのです。同様に、会社設立に必須である商業登記についても、司法書士の専管業務とされているため、行政書士にはできません。
また、労働や社会保険について、申請手続きを代行したり申請書類を作成したりすることも、対象外です。これらは社会保険労務士(社労士)という、別の士業の独占業務となっているからです。就業規則の作成はできますが、それを元にした労働基準監督署への申請は、ご自分でやるか社労士に依頼するか、ということになります。

等身大のコンサルティング
実際には、書類を作る前の段階で、お役に立てるのではないかと思います。
もう四半世紀も前になりますが、私(代表の山田)もクリエイターとして独立した日があります。あの頃は情報源が少なくて、会社を作るか個人でやるかといったあたりから、全てが手探りでした。帳簿を作ったものの、講師報酬をどの費目にするのかで大いに悩んだものです。
インターネットが普及した今では、逆に情報の洪水の中を泳ぎきらないといけないと言えるでしょう。フリーランスでやっていく人も、また会社を起こそうという人も、逆方向の困惑があるのではと思います。
コンサルタントというと、「MBA学位をひけらかす“上から目線”の超高収入ビジネスエリートが、データ分析とフレームワーク振りかざして、リストラ断行を迫る」なんてイメージがありますが(偏見過ぎますか?)、クリフェが提供するコンサルティングは、そのような大上段に振りかざしたものではありません。あくまでも「等身大」。依頼者様と同じ位置に立って、一緒に考え、アドバイスしていくものです。