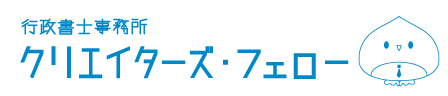共同制作の著作物について
楽しいサークルだからこそ
こんにち、同人と商業の世界は無関係ではなく、相互に行き来し合う相補的な存在です。商業作品に触発された二次創作分野が同人の中心と言える一方で、同人発のコンテンツが商業分野で取り上げられメジャー化していくなんてことも、珍しいことではなくなりました。
このような中、とても気にかかることがあります。共同で制作された著作物について、参加したメンバー間で権利関係の合意をどう図っているのかということです。
例えば、気の合う仲間が集まってゲームを作るとします。自分たちだけで楽しむつもりで始めたとしても、完成したら公開しますよね。そして、自信作なら有償頒布するでしょうし、その先だってあります。評判が高まると、メジャーなパブリッシャーのプロデューサーからコンタクトが来るかもしれません。ところがこうなってくると、権利関係が問題になってくるのです。

平等か、公平か
例えば、企業に対してライセンス許諾を出すとします。この分け前をどう配分すべきでしょうか。
同人サークルは、好きな者同士の寄り集まりで、平等が原則でしょう。とはいえ、できあがった作品がもたらす結果に対しても、平等がふさわしいでしょうか? 力量も作品に注いだ努力も全て均等…なんてことはまずなく、成果に対する現実の貢献度は、人によって違います。能力差は当然ありますし、取り組み姿勢もまちまち。「最初の頃の話し合いには熱心に参加してたけど、実際に作り始めたら来なくなった」なんてメンバー。途中から参加して気づいたら主導的な立場になっていたなんてメンバー。さらにはいることはいるけど、ほとんど何もしないなんてメンバーもいるでしょう。その全員を相手に「収入は山分け」なんてやり方で、ほんとうに全員が満足できるのでしょうか?

法的な扱いは面倒
特段の合意がない場合、法律上、共同作品の著作物は「共有」のような扱いになります。各自、自分自身のために使うことができるのですが、著作者人格権も全員が持つことから、一人でも不満な人がいれば、その作品は事実上利用できません。ライセンス許諾ばかりでなく、公開や続編・スピンオフ作品の制作などもできなくなってしまうのです。
トラブルを防ぐために有効なのは、メンバー全員が合意できる条件を、早い段階でまとめておくことです。これは事前でも事後でもかまいません。また、口約束でも有効ですが、そもそもがトラブルへの備えですから、文書化しておくべきでしょう。「協定書」「覚書」「参加ルール」どんな名前でも法的効果は同じで、契約書の一種となります。
でも、誰から話を切り出すのか、また誰が原案を作るのかなど、とっても難しいですね。そこで専門職である第三者の存在が、役に立つのです。
権利関係書類の作成は、行政書士の法定業務です。その意味で行政書士であれば誰でもできるのですが、クリフェには「創作を知っている」という強みがあります。