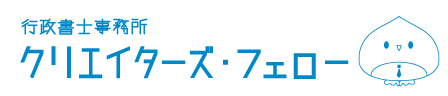活動と法的リスク
リーガルリスクの存在
こんにち、企業の多くは、弁護士と顧問契約を結んでいます。企業活動というのは、それがどんな分野であっても、一定のリーガルリスクを持っているということです。一方で、弁護士の顧問料は意外なほど安いので(調べてみると月3~5万円程度です)、企業活動に伴うコストとしては問題にならないというところでしょうか。
同人もまた社会的活動をする単位です。ただ、顧問弁護士がついているサークルはまずないでしょう(弁護士自身が趣味で同人活動をしている可能性はありますが)。ではプロじゃないから法的トラブルなどいっさい考えられないのかというと、まあそういうわけにも行きませんよね。何しろ、トラブルというのは災害と同じで、たいていは向こうからやってくるのです。
また、企業であれば、一定規模のバックオフィスも持っていますが、同人は創作のみならず製作の全方面まで単独でしなければなりません。

商業リアリズムの功罪
また、同人界には、同人ならではの独自事情も存在します。
産業界には「現実の力関係」というものがあり、強い立場の会社の意思が、全体の多数意見や場合によっては法解釈よりも優先されたりします。また、組織内部においても、役職や所属部署などのしがらみが、関係者を束縛します。
この点、同人は本質的に自由で、そして平等です。メジャー作品を飛ばしている売れっ子作家も、コミケ会場に来れば同じ「サークルさん」。一人の個人として対等な立場で付き合う……とても素晴らしい慣行です。
ただ、産業界のリアリズムも、「秩序」という点ではメリットがあるのです。現実の力関係によって慣習が形成されていたりします。また、業界を牛耳っている会社が、トラブルへの裁定者にもなりえます。
同人界では、それがありません。その結果、もめ事が泥沼化しやすい要因を、あらかじめ持っているとも言えるのです。

活動そのものへ
そもそも法の視点から言えば、同人サークルの立場は、本質的に不安定です。純創作のサークルも多数ありますが、全体の中心が二次創作にあることは事実。そしてこれが知財法の権利規定と抵触することも事実です。一都市の人口ほどの来場者を集めるメガイベントであるコミケなど、教条的な遵法論者の目には、「世界最大の闇市」としか映らないでしょう。
現実問題として、メディア産業に属する大半の会社は、自社保有コンテンツの二次創作について、それほど問題視していません。しかし、全ての会社がそうでないことは、ご承知でしょう。また、今許容している会社が、かつては強硬な立場をとっていたという例も、ご存じの方は多いと思います。この態度が逆転するのかしないのか、ひとえにその会社の方針次第です。
また、ビジネスとしてガチガチになっている昨今のクリエイティブ業界を考えると、そう安心もしていられないとも思うのです。「黙認」というのは、している側が積極的に主張することはありません。されている側の一方的な解釈です。サークル側が「黙認してくれているから」と思っていても、いつ突然風向きが変わるともしれないのです。

まずはご連絡ください
「相談無料」とはうたっていないクリフェですが、受任に至るまでの途中段階で料金が発生することはありません。一般論の範囲内であれば業務とは無関係でお答えできますし、参考になる事例の紹介もできるでしょう。
また、別ページにまとめている価格表ですが、実際には案件によって個別に考えますし、特にアマチュアや学生さんの場合には、低廉で済ませられるようなオプションも用意しています。
そんな訳なので、まずはご連絡ください。「これって仕事になるの?」という疑問を持ったままで結構です。