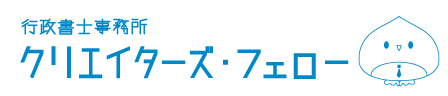その名も八士業
剣を持たないサムライたち
士業という言葉は、通常は「しぎょう」と読みますが、武士の士に通じることから「さむらいぎょう」と読む場合もあります。「法学部はサムライになる学部」なんて、昔はよく言われたものです。
ただ、最近は“隣接法律専門職”という言葉も使われます。というのも、「士」で終わる国家資格というのが実に多くて、数で言えば法律と無関係なサービスを提供するものが圧倒的なのです。例えば電気工事士とか歯科衛生士とか、おなじみですよね。

人呼んで八士業
伝統的な意味での士業(弁護士&隣接法律専門職)は、次の8つになります。
| 弁護士 | 法廷に立つ。法律相談や法律鑑定も。 |
|---|---|
| 司法書士 | 不動産や会社の登記。過払い金訴訟でもおなじみ。 |
| 行政書士 | 許認可業務、入管業務。また各種文書作成。 |
| 税理士 | 税金関係の申請書作成や企業会計など。 |
| 弁理士 | 特許や商標の出願。知財契約の代理。 |
| 社会保険労務士 | 労働&社会保険の事務代行。 |
| 土地家屋調査士 | 土地家屋の調査・測量。 |
| 不動産鑑定士 | 不動産価値を評価。 |
隣接法律専門職というくらいなので、専門業務はどれも法律に関係しています。しかし「法律家」と呼べるのは、弁護士/司法書士/行政書士の3つです。他の士業は特定領域のスペシャリストで、それぞれの分野においては唯一無二の存在になりますが、一般的な法律業務には対応しません。実際、憲法・民法・商法をきちんと試験科目に含んでいるのは、この3つだけなのです。

これあってこその“業務独占”
八士業には、重要な特徴があります。「業務独占」と言って、その士業の人でないと報酬をもらってやってはいけない特定の仕事が、それぞれに指定されてるのです。
行政書士の場合、法に書かれている仕事は次の4種類です。
- 官公署に提出する書類を作成する
- 権利義務や事実証明に関する書類を作成する
- 官公署への提出や許認可関係の手続きを代理する
- それらについて相談に応じる
ただ、除外規定があり、他の士業の業務独占でないものに限るとされています。これがけっこう利いてきまして、例えば次のようなことは、報酬をもらってやるのはだめです。
| 一般的な法律相談、鑑定 | これは弁護士だけ。 |
|---|---|
| 裁判所や法務局に提出する 書類の作成 | これは司法書士だけ。 |
| 裁判の代理人になる | 基本は弁護士。少額であれば司法書士もできるけど、行政書士はだめ。 |
| 税金関係 | 税理士だけ。(※酒税などごく一部例外的に可) |
| 社会保障関係 | 社労士だけ。(※社労士制度ができる前に開業した人には可) |
| 特許庁への出願 | 弁理士だけ。(権利移転等の書類の申請は可) |

士業って、8種類だけ?
八士業といいますが、本当に8つだけなのでしょうか。実はこのあたりは曖昧で、公認会計士と中小企業診断士を加えて「十士業」と呼ぶ場合があります。一方、不動産鑑定士を除き、代わりに海事代理士(商船・漁船の登録などをします)を入れたものを「八士業」とすることもあります。よく見かけるまとめで最大のものは「12士業」。これは、十士業に建築士と社会福祉士を加えたものです。
このゆらぎの理由は、“n士業”の基準として何に注目するかによるものです。
職務請求権に注目すれば、それを持たない公認会計士や不動産鑑定士は外れるということになります。一方、市民生活での重要度という視点では、特定業界対象のB2Bビジネスしかしない海事代理士はわざわざピックアップする必要がないということになるでしょう。また、12士業は、市民向けの合同説明会などで使われています。相続や介護などに注目したまとめと言えるでしょう。
見ようによっては何より重要なのが、その言葉自体の「産業利用価値」です。実際にn士業の言葉をいちばん使うのは大人向け受験産業で、彼らの視点では売り込みやすい資格の方をピックアップしたくなると思います。業務独占を持たない中小企業診断士を入れるのも、お客に売り込みやすいからでしょう。

ワンストップ化という流れ
士業の違いは、実は監督官庁の違いでもあります。
司法書士は法務省、弁理士は特許庁…といったように、多くの士業には、監督責任を持つ官庁があります。行政書士も例外ではなく、直接的には都道府県知事で、その結果として地方自治体を統括する総務省が、中央官庁における所管となります。
これは、サービスを利用する国民からすれば面倒な話です。そこで、あちこち立ち寄らなくても一カ所で全て済むようにする=ワンストップ化ということが、叫ばれています。
これは究極的には政策論になってしまうのですが、今ある“士業界”も、現実に二通りの方法で対応しています。
一つが、合同事務所です。複数の士業が集まって一つの大きなオフィスあるいはビルに入り、利用者の便宜を図るというもの。ただ、各士業には法律上の守秘義務があるため、依頼人の情報や依頼内容を勝手に融通するわけにはいかず、「移動する手間が省ける」以上のメリットがない場合もあります。
そしてもうひとつが、ダブルライセンス。例えば行政書士が同時に司法書士にもなるように、複数の士業として同時に登録することで、両方の専管業務に対応するというものです。さらに、他士業の人を雇用することで、法人としての事務所自体がマルチライセンス化するということもあります。
ワンストップ化を政策論として徹底すると、士業の統廃合ということになるのでしょう。それはそれで、大きな問題になってしまいそうです。
*1 行政書士は、なぜか行政書士以外に雇用されることが許されていません。そのため、他士業の事務所に雇用されることもできませんし、「社内行政書士」になることもできません。ワンストップ化が進む過程で仲間はずれにされるのではないかと思うのですが、とにかくこういう決まりです。