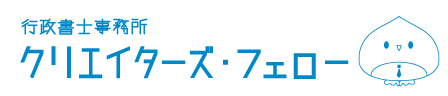知財とくれば弁理士?
知財の専門家って弁理士では?
トウキョウトッキョキョカキョク…なんて早口言葉、今の子供たちは遊んでるのでしょうか? ともあれ、こんな言葉の存在からも、特許権はぐっと身近な存在ですね。
特許権は、商標権などと合わせて「産業財産権」と呼ばれています。弁理士は、これらの登録出願代理を独占業務とする仕事です。また、産業という視点で知的財産権が論じられる場合、その中心にあるのは特許権です。そのため「知財とくれば弁理士」というイメージが浸透しています。
ただ、弁理士の独占業務となっているのは、あくまでも出願の部分。取得した特許権を実際にビジネスにする局面では、ライセンス契約などが必要になってきますが、こういう仕事についての独占権を持っているわけではありません。

産業財産権と知的財産権の違い
ここで、ちょっと細かい話を。先ほど「産業財産権」と書きました。これと知的財産権の関係は、集合記号で言えば「⊂」。つまり、知的財産権という大きな括りの中に、産業財産権が含まれている、そういう関係です。
知的財産権と総称されるものは、次のようになります。
| 1.特許権 | 発明に対して与えられる権利。 |
|---|---|
| 2.実用新案権 | 発明ほど高度でない改良等に関する権利。 |
| 3.意匠権 | 工業デザインに対して与えられる権利。 |
| 4.商標権 | 商品名や商品形状などを保護する権利。 |
| 5.育成者権 | 花や農産物の新品種を育成する権利。種苗法で規定。 |
| 6.回路配置利用権 | 半導体集積回路の回路配置に関する権利。半導体回路配置保護法で規定。 |
| 7.著作権 | 著作物に関する権利。 |
1~4は、かつては「工業所有権」と言いました。ただ、現実には工業ばかりでもなく、また民法上の所有権とはやはり異なりますから、いつしか「産業財産権」と呼ばれるようになったのです。
これらは、別個の法律で規定されています。そして所管官庁も一つではありません。1~4が特許庁、5が農林水産省、6が経済産業省、7が文化庁です。
登録申請(出願)が弁理士の専管業務となるのは、特許庁に出すものになります。つまり、1から4までです。

共管業務と専管業務
知財に関する契約書の作成や、登録されている産業財産権の移転等の申請は、弁理士の仕事の中で、行政書士と重なる部分です。こういうものを共管業務といいます。
一方で、弁理士と弁護士の共管業務も存在します。代理人として行う契約交渉です。一般に、代理人として相手方との交渉を行えるのは弁護士だけなのですが、こと知財関係の契約については、弁理士も交渉資格を持っています。
さて、“共管”業務であり、“競管”業務ではない点に、ご注目を。
そもそも士業というのは、競業ではなく協業する関係にあります。
弁理士という仕事は実のところ理系寄りです。試験合格者の8割が理工系の出身ですし、合格者数上位校には東工大や東理大がはいっています。特許という理工系分野を中心の仕事にしていることから、そうなってくるのです。その反面、法律家としてのバックボーンは、必ずしも十分に持っているわけではありません。民法は取引において不可欠の最重要法規なのですが、弁理士試験では二段階目にのみ関係する選択科目の一つに過ぎず、理工系の人だとそもそも勉強自体していないでしょう。
争訟が想定されたり、あるいは扱う金額などが大きい場合には弁護士と、それほどでもない場合は行政書士と、それぞれ共同して仕事をするというのが、制度自体の基本設計と言えるかもしれません。