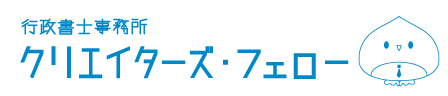士業の盟主、弁護士
別格の法律職
行政書士は法律を対象にしている専門職ですが、同じ領域の“同業者”に「弁護士」という存在があります。とても高い社会的ステイタスを持つ職業ですが、士業という視点でも別格の存在です。
- 唯一無二の専管業務を持つ
- 試験の受験資格が厳しい
- その試験自体が格段に難しい
弁護士になるためには、司法試験の合格が必要です。これは学部卒では受けられず、法科大学院修了が受験資格。著名な法科大学院は入学選考が厳しいのですが、それを出た人にとってすら難しいのが司法試験。東大・京大の法科大学院で、どうにか50%程度の合格率……と言えば、難しさもおわかりいただけるのではないでしょうか。しかも、合格した後は司法修習というのを1年間受けなければいけません。裁判所・検察庁・法律事務所をたらい回しにされる実務研修で、この終了時点でさらに試験があり、ここでも5%程度は落とされるという厳しさです。

弁護士の専管業務
法律家としての弁護士は、ほぼオールマイティな存在です。他士業に属する仕事の多くをすることができます。そして、先述の通り、他を寄せ付けない専管業務を持っています。具体的には、次の3つです。
- 法律相談それ自体を、プロとして受けることができる。
- 依頼主の代理人として相手方と交渉できる。
- いざとなったら裁判を遂行できる。
2と3は、「弁護士=戦う仕事」と見ることができます《*1》。代理をするというのは、持てる知識と技術の全てを使って依頼人にとって少しでも有利な結論を導くということです。実際に法廷に出ることは多くないようですが、それを辞さない態度で事に臨むため、先方にとっては手強い相手となり、依頼人にとっては頼もしいパートナーとなるわけです。このように見てみると、1も無関係ではありません。法律を使った戦いの専門家として、勝てるかどうかをアドバイスする仕事であるとも言えるからです。
この点行政書士はどうかと言いますと、まず交渉することができません。当事者の代理として契約書作成もしますが、合意が成立した場合にその合意を文書化する仕事です。合意に向けての提案を依頼主にすることはできても、依頼主の立場に立って相手方と交渉することはできないのです。また、行政庁への許認可申請も、却下・棄却された場合の不服申立てまでは代理できますが《*2》、裁判になったら弁護士に任せるしかありません。
*1 2と3は部分的に他士業にも認められています。
*2 特定行政書士の指定を受けた人に限ります。

実はそんなに余っていない
近年「弁護士余り」という言葉が、メディアではよく踊っています。数字だけをみると、確かに激増しています。司法試験制度の改革前は全国に1万人程度だったのですが、現在では4万人超。人数だけで言えば、司法書士の二倍、行政書士(4万9千人)にも近づきつつあります。
このような理解を背景に「何でも弁護士にやらせればいいじゃん!」という見解が現れてきています。
でも実際のところ、弁護士はそんなに余っているのでしょうか?
実際には偏りが大きいのです。
まず、弁護士の世界には大規模なローファームというものがあります。トップクラスになると、何百人もの弁護士を擁していて、5大ローファームを合計した数は軽く2千を超えています。その一方で、インハウス・ロイヤーと呼ばれる人がいます。メーカーや金融機関などの大企業に社員として雇用されている弁護士です。こちらも2千人を超える規模で、合わせると弁護士全体のうちの1割の人が、これら大手法人の所属と言うことになるのです。
そして、もう一つの偏りが、地理的要素です。4万人を超える弁護士ですが、東京・神奈川だけで、実に半数の弁護士が所属しています。
週刊誌などで言われる“弁護士余り”現象というのは、具体的には「資格とっても食えない人が出現している」現状を言い表しているようです。でも昔だって、別に資格さえあれば誰でも左うちわだった訳じゃなく、皆それぞれに苦労されていたと思うのですが、どうでしょうか?

「弁護士さえいればいい」じゃないもう一つの理由
法律家としての“持てる力”という点では、あきらかに弁護士の方が上です。また、法律の知識も、概して高水準でしょう。
でも、現実に解決したい問題は、法律だけで決まってくるわけではありません。「弁護士」という“武器”は鋭利すぎ、ときに問題をこじらせてしまう場合があります。通常の交渉の席に弁護士が同席していたら、「けんか腰」と解釈されるでしょう。
そしてもう一つ。この鋭さは、自分の方も切り裂く危険性があるということです。
士業は、依頼人のためにベストを尽くします。そして戦う仕事である弁護士にとってのベストは、相手を叩きのめすことです。これは彼らに求められる職業倫理の一つで、「ハイアード・ガン」といいます。この精神が契約書作成という局面で発揮される場合、「依頼主にとって少しでも有利な条件を盛り込む」ことになります。ところが、これがビジネスのコアな価値である「クリエイターからの信頼」を破壊してしまうことにつながるのです。
当事務所代表の私も、フリーランスだった時代、嫌な思いをしたことがあります。それまでいい関係を築いていた会社から、突然新様式の契約書が押しつけられ、その中には「本契約の期間中に甲が作成したアイデア等の全ての権利は会社に譲渡するものとする」といった、噴飯ものの条件が載せられていたりしたのです。いきさつを聞いてみると、出てくるのは弁護士の名でした。
そして訂正を求めても、持ち戻った担当者の口から出てくるのは「弁護士が“念のためそうしておけ”というから」という理由でのゼロ回答でした。
彼らにとって、クリエイターなどしょせんは“出入り業者”に過ぎず、その利益を根こそぎ吸い取ることこそが依頼人の利益、となるのでしょう。しかし、クリエイティブ産業が関わるようなビジネスは、一方の損失が他方の利益になるような関係ではありません。クリエイターはむしろ顧客にも似た存在で、ブランドロイヤリティの構築こそがビジネスの原動力になっているのです。それを破壊するような行為は、「試合に勝って勝負に負ける」という言葉を地で行くものと言えるでしょう。

違うのは、役割
弁護士も、行政書士そして司法書士も、広い意味での法律家です。これは、医師とコ・メディカルの関係をイメージされるといいでしょう。医師法上、医師は医療行為を独占していますが、一方で「医療そのものではないけど医療的なこと」への需要も根強いものがあります。多くの整形外科医院は、理学療法士が常駐するリハビリセンターを併設していますが、むしろこちらの方が人気だったりしますね。他、柔道整復師や鍼灸師の存在も重要です。骨が折れているような場合なら医師にかからないとだめですが、そうでない――例えば寝違えて首が痛いといった場合は、鍼や整体の方が優先的選択肢です。同じようなことが、隣接法律専門職にも言えるのです。
そして、現実的に費用の問題もあります。弁護士は法律相談そのものも業務なので、単に話を聞いてもらうだけでも料金が発生します。ざっと調べてみたところ、初回の相談を30分あたり5千円で設定している事務所が多いようです。まあ、弁護士に相談するほどのこじれた内容が30分で解決するはずはないので、実際には2時間=2万円ぐらいはかかるのでしょう。これは、確かに、高度な専門職を拘束する時間単価としては破格の安さですが、支払うお客さんにとっては決して小さな額ではありません。最終費用がせいぜいそのぐらいで済む行政書士の存在は、リーガルサービスそのものを人々にとって身近なものとする上で、大きな役割を果たしていると言えるのではないでしょうか。